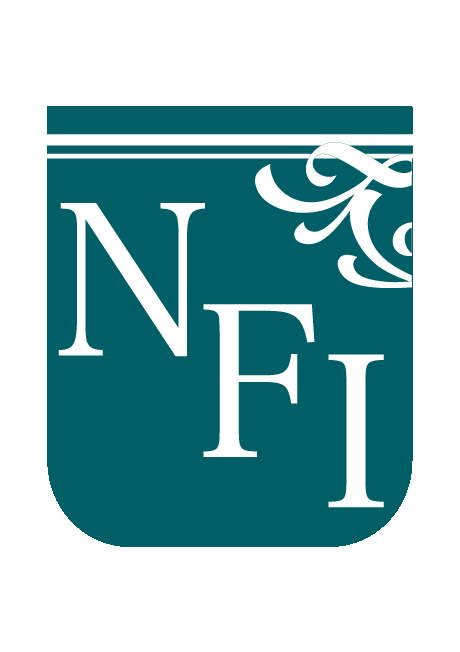New Food Industry 2025年 67巻 5月号
原著
ピロロキノリンキノンジナトリウム(PQQ)摂取後の20から65歳の健康な成人に対する 認知機能と安全性の評価
杉本 淳 (SUGIMOTO Atsushi),池本 一人 (IKEMOTO Kazuto),永松 健太郎 (NAGAMATSU Kentaro) ,美野 晃輝 (MINO Koki),中村 振一郎 (NAKAMURA Shinichiro)
Cognitive Function and Safety of Pyrroloquinoline Quinone Disodium (PQQ) in Healthy Adults Aged 20 to 65 Years
Authors: Atsushi Sugimoto 1, Kazuto Ikemoto 1, Kentaro Nagamatsu 1, Koki Mino 1 , Shinichiro Nakamura 2
* Corresponding author: Takuro Maeno
Affiliated institutions:
1 Niigata Research Laboratory, Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.
[182 Tayuhama, Kita-ku, Niigata City, Niigata 950-3112, Japan]
2 Kumamoto University, Graduate Institute for Frontier Sciences, KAKETSUKEN Endowed Chair
[2-39-1 Kurokami, Chuou-ku, Kumamoto City, Kumamoto 860-8555, Japan]
Abstract
Research on dietary supplements aimed at improving cognitive function is actively being conducted, and among these, Pyrroloquinoline Quinone Disodium (PQQ) has attracted attention. PQQ has functions related to mitochondrial biogenesis and neuroprotection. Cognitive tests targeting middle-aged and elderly individuals have been reported so far. A double-blind, placebo-controlled trial was conducted with healthy adults aged 20 to 65 years, including individuals in their 20s and 30s, to assess the effects of taking 20 mg of PQQ daily. Cognitive function evaluations using the Stroop Test, 2-back Test, and computerized neurocognitive assessments (Cognitrax), as well as safety assessments including adverse events, biochemical tests, and blood tests, were performed. The collected data were analyzed based on medical statistics. The Stroop Test measures attention and judgment. In the Stroop Test, the PQQ intake group showed improvements in accuracy and response time after 12 weeks of intake. There was no significant difference observed in the 2-back Test. In the neurocognitive tests, improvements were noted in composite memory and verbal memory. No significant differences were observed between the placebo and PQQ intake groups in adverse events, biochemical tests, blood tests, and urine tests. It was confirmed that PQQ improves attention, judgment, composite memory, and verbal memory in healthy individuals aged 20 to 65 years and is safe.
要約
認知機能の向上を目指した栄養補助食品の研究が盛んに行われており,その中でもピロロキノリンキノンジナトリウム(PQQ)は注目を集めている。PQQはミトコンドリア新生や神経保護作用の機能を有する。これまで中高年を対象とした認知試験が報告されてきた。対象年齢に20,30代を加えた20から65歳の健康な成人を対象にPQQ1日20mg摂取による2重盲検プラセボコントロール試験が行われた。ストループ試験,2バック試験,コンピューターによる神経認知評価(Cognitrax)による認知機能評価と有害事象,生化学検査,血液検査の安全性評価試験が行われた。これらのデータを入手し医学統計に基づき解析した。ストループ試験は注意力と判断力を測定する。ストループ試験では摂取後12週間後PQQ摂取群は正解率と回答時間に改善がみられた。2バック試験では有意差は見られなかった。神経認知試験では総合記憶,言語記憶に改善がみられた。有害事象,生化学検査,血液検査尿検査においてプラセボとPQQ摂取群に有意差はなかった。PQQは健康な20才から65歳の成人に対し,注意力と判断力,複合記憶と言語記憶を改善する効果を有し,安全であることが確認できた。
解説
クロスオーバー比較デザインにおいてt検定を主解析に採用する方法
馬場 亜沙美(BABA Asami) ,鈴木 直子(SUZUKI Naoko),野田 和彦(NODA Kazuhiko), 波多野 絵梨(HATANO Eri),髙橋 徳行(TAKAHASHI Noriyuki),新林 史悠(SHINBAYASHI Fumiharu) , 板橋 怜央(ITABASHI Reo) ,柿沼 俊光(KAKINUMA Toshihiro),山本 和雄(YAMAMOTO Kazuo)
Method for Adopting t-Test as the Primary Analysis in Crossover Design.
Authors: Asami Baba 1*, Naoko Suzuki 1, Kazuhiko Noda 1, Eri Hatano 1, Noriyuki Takahashi 1, Fumiharu Shinbayashi 1, Reo Itabashi 1, Toshihiro Kakinuma1, Kazuo Yamamoto 1
* Corresponding author: Asami Baba1
Affiliated institutions:
1 ORTHOMEDICO Inc.
クロスオーバー比較デザインは,ランダム化比較試験(RCT)の一形態であり,試験参加者自身を対照とする点が特徴である。試験参加者は異なる介入条件を順次受けることで個人間のばらつきを抑え,高い統計的検出力を実現する。よく使用されるクロスオーバー比較デザインは,試験参加者をランダムに2つの群に分け,群1は介入A⇒介入B,群2は介入B⇒介入Aの順序で介入を受ける2×2クロスオーバー比較デザインである。そして,それぞれの群における結果を比較することで,介入の効果を評価する。特に生物学的同等性試験や薬物動態試験で用いられ,その有用性が広く認識されている。しかし,条件間の影響(持越効果)や試験参加者脱落といった課題も伴う。
クロスオーバー比較デザインにおける解析方法としては,一般的に分散分析(ANOVA)が使用され,介入効果,持越効果,時期効果が評価される。しかし,ANOVAの計算過程は煩雑であり,専用の統計ソフトを用いる必要がある場合が多い。そのため,より簡便で実務的な解析手法が求められる場面も少なくない。そこで本稿では,クロスオーバー比較デザインにおけるANOVAの代替として,t検定を主解析手法として採用する方法を提案する。
解説
クロレラによるダイオキシン類およびメチル水銀の排泄促進作用
Effect of Chlorella intake on the excretion of dioxins and methylmercury
丸山 功(Isao Maruyama)
クロレラは緑色植物門に属する単細胞藻類であり,たんぱく質含量が高く,ビタミン,ミネラル,必須脂肪酸,カロテノイド,食物繊維,葉緑素などの栄養成分を豊富に含む。1960年代以降,ヒトや動物に対する生理作用に関する多数の研究が行われ,多様な栄養素を補給できると共に,生活習慣病の予防・改善,生体防御調節,酸化ストレスの低減,解毒などの多様な効果が報告されている1)。
クロレラの解毒作用に関しては,鉛やカドミウムなどの有害重金属2),ダイオキシン類3, 4)やメチル水銀5, 6)などの有害化学物質の排泄を促進することが報告されている。ダイオキシン類とメチル水銀は,過去に食中毒および公害の原因物質として深刻な健康被害をもたらしたが,ダイオキシン類は厳しい排出規制によって環境中の濃度は減少し,水銀も環境中への排出と工業的な水銀の使用が削減されたため,通常の環境下で成人の健康を害する恐れはなくなった。一方で,地球環境・海洋において低濃度の汚染は継続しているため,母乳で育てられている第一子は,発育に明らかな影響は確認されていないものの,生後1ヶ月の時点でダイオキシンの耐用一日摂取量の約10倍を摂取している7)。また,胎児の健全な発育のために,妊婦を対象としてメチル水銀濃度の高い魚の摂取に関する注意が公表されており8),次世代を担う乳児や胎児において課題が残されている。
シリーズ 世界の健康食品のガイドライン・ガイダンスの紹介
―欧州食品安全機関 (EFSA).心血管機能と血圧・血中脂質の改善に関する機能性評価―
馬場 亜沙美 (BABA Asami),鈴木 直子 (SUZUKI Naoko),野田 和彦 (NODA Kazuhiko),波多野 絵梨 (HATANO Eri),髙橋 徳行 (TAKAHASHI Noriyuki),新林 史悠(SHINBAYASHI Fumiharu),板橋 怜央 (ITABASHI Reo),柿沼 俊光 (KAKINUMA Toshihiro),山本 和雄 (YAMAMOTO Kazuo)
Introduction to Guidelines or Guidance for Health Food Products in the World: European Food Safety Authority (EFSA) series —Functional Assessment of cardiovascular health—
Authors: Asami Baba1*, Naoko Suzuki1, Kazuhiko Noda1, Eri Hatano1, Noriyuki Takahashi1, Fumiharu Shinbayashi1, Reo Itabashi1, Toshihiro Kakinuma1, Kazuo Yamamoto1
*Correspondence author: Asami Baba
Affiliated institution:
1 ORTHOMEDICO Inc.
[2F Sumitomo Fudosan Korakuen Bldg., 1-4-1 Koishikawa, Bunkyo-ku, Tokyo, 112-0002, Japan.]
前回(2024 Vol.67 No.2 掲載,『シリーズ 世界の健康食品のガイドライン・ガイダンスの紹介―欧州食品安全機関(EFSA). 食欲と体重・体脂肪のコントロールに関する機能性評価―』)に引き続き,欧州食品安全機関(European Food Safety Authority: EFSA)の発行するガイダンス(以下,EFSAガイダンス)について紹介する。今回は,EFSAガイダンスの『Guidance for the scientific requirements for health claims related to antioxidants, oxidative damage and cardiovascular health(Revision 1)1)』の「3.3. Function claims related to cardiovascular health」に記載されている,心血管機能と血圧・血中脂質に関する機能性評価についてまとめた。 血中脂質,動脈血圧,動脈の弾性,血管内皮機能,血漿ホモシステイン濃度,血小板凝集および静脈血流における有益な変化を含む,心血管系の健康に関する一般的なヘルスクレームを科学的に実証するために,多くのアウトカムが提案されている。これらは,ヒト試験における確立された方法により評価することができ,心血管系分野における特定の機能を科学的に評価することができる。
本稿では,心血管系の健康に関連するヘルスクレームの根拠となるヒト試験の特徴に焦点を当て紹介する。
解説
Genotoxicity test of Ganoderma lucidum using a microbial mutagenicity test (Ames test)
Authors: Yeunhwa Gu 1*, Takenori Yamashita 2 and Tota Inoue 3
* Corresponding author: Yeunhwa Gu 1
Affiliated institutions:
1 Department of Radiological Science, Graduate School of Health Science, Faculty of Health Science Junshin Gakuen University
2 Graduate School of Health Science, Suzuka University of Medical Science
3 Mie breathing swallowing rehabilitation clinic
Abstract
The Ames test is a mutagenicity test that examines the ability of natural substances to act on the DNA of cells and cause damage to their base sequences. The Ames test is a testing method developed by Dr. Ames of the United States. The principle of the Ames test is that when a mutant strain of Salmonella typhimurium, which cannot grow without the essential amino acid histidine [called histidine-requiring (His-)], is cultured with a substance, if the substance is mutagenic, a reversion occurs during the division process of the bacteria, and the bacteria become histidine-nonrequiring (His+). As a result, the bacteria form colonies to continue to grow by self-producing histidine, and by counting the number of these colonies, it is easy to know whether the tested substance will suddenly cause an abnormality. Cannabis sativa L., which belongs to the Cannabaceae family, has been thoroughly studied for its various efficacy. In this study, the genotoxicity of Ganoderma lucidum extract 160.32 mg/mL was examined. Mice were treated with three doses of the extract (500, 1000, 2000 mg/kg bw) or with a negative control. The control group was administered placebo orally and cyclophosphamide monohydrate (20 mg/kg bw) was administered orally. It was used as a positive control by intraperitoneal injection. Blood was used for the comet test. The animals were then euthanized for collection of bone marrow for micronucleus testing. Extracts were replicated in TA100 or TA98 at 375, 250, 125, and 62.5 μ/plate. It did not increase the number of mutant bacterial colonies, but rather the number of micronucleated polychromatic erythrocytes (MNPCEs). The study did not affect the polychromatic erythrocyte to normochromatic erythrocyte ratio (PCE/NCE). Furthermore, there was no change in the indices or frequency of DNA damage in hematopoietic cells. The results indicate the absence of genotoxic effects. Machine Translated by Google Genotoxic agents are substances that interact with DNA and induce changes in its structure or function. If these changes are permanently fixed and passed on to future generations, they are genotoxic. are known as mutations. Mutations are responsible for genetic variation, It is essential for the survival of the species. Several studies have demonstrated that the expression of various chromosome-associated factors The results were negative, and this finding indicates that MAK is genotoxic. Other safety tests include the following safety tests for MAK: Ganoderma lucidum extract (MAK) has shown negative results in genotoxicity tests, suggesting its safety. However, detailed genotoxicity data on Ganoderma lucidum itself and other extracts are limited. Further research and application of standardized test methods may be necessary to more reliably evaluate the safety of Ganoderma lucidum.
霊芝に対する微生物を用いた 変異原性試験(Ames試験)の遺伝毒性試験
具 然和 (GU Yeunhwa)*,山下 剛範 (YAMASHITA Takenori)2,井上 登太 (INOUE Tota)3
要旨
Ames 試験は,つまり変異原性試験とは天然物質等の細胞がもつDNA に作用して,その塩基配列に損傷を引き起こす性質を調べた。Ames試験とはAmes試験の米国のAmes博士が開発した試験方法である。Amesテストの原理は,必須アミノ酸のヒスチジンがないと生育できない(ヒスチジン要求性(His-)という)変異株のネズミチフス菌を,物質と一緒に培養すると,物質に変異原性があれば,菌が分裂する過程で復帰突然変異が起こりヒスチジン非要求性(His+)になる。その結果 ,菌はヒスチジンを自己生産し増殖を続けるためコロニーを形成するので,このコロニー数を計測することにより,容易にテストした物質が突然異変を起こすか否かを知ることができる。アサ科に属するカンナビスサティバL.は,その多様な効能について徹底的に研究されてきた。この研究では,霊芝抽出物160.32 mg/mLの遺伝毒性を調べました。マウスを用いて抽出物の3つの用量(500,1000,2000 mg/kgbw)または陰性対照(プラセボ)を経⼝投与し,シクロホスファミド⼀水和物(20 mg/kgbw)を腹腔内注射による陽性対照として使用しました。⾎液はコメットテストのために採取され,動物は小核テストのために⾻髄採取のために安楽死させられた。抽出物は,TA100またはTA98で(375,250,125,および62.5µg/プレート)で復帰突然変異細菌コロニーの数を増加させず,小核多染性⾚⾎球(MNPCE)の数や多染性⾚⾎球と正染性⾚⾎球の⽐率(PCE/NCE)にも影響を与えなかった。また,造⾎細胞におけるDNA損傷の指標または頻度も変化しなかった。これらの結果は,遺伝毒性効果がないことを⽰すものである。効果があり,治療への応用の可能性を裏付けている。遺伝毒性物質はDNAと相互作用し,その構造や機能に変化を引き起こす物質である。これらの変化が永久に固定され,将来の世代に受け継がれる場合,それは突然変異として知られている。突然変異は遺伝的多様性に関与しており,種の⽣存に不可欠である。いくつかの研究では,さまざまな染⾊体関連因⼦への損傷が見つかっている。結果は,陰性であり,この結果は,MAKが遺伝毒性を示さないことを示唆している。その他の安全性試験については,MAKについては,以下の安全性試験も実施されている。霊芝抽出物 (MAK) は遺伝毒性試験で陰性結果を示しており,安全性が示唆されている。しかし,霊芝そのものや他の抽出物についての詳細な遺伝毒性データは限られている。霊芝の安全性をより確実に評価するためには,さらなる研究と標準化された試験方法の適用が必要かもしれない。
解説
Recent Interest Rate Differentials between Japan and the United States and Their Impact on Exchange Rates and Prices Inflation in Japan
Ryusuke Oishi
Abstract
Japan’s price level rose in 2024, creating a burden for consumers. The policy interest rates set by each country’s central bank affect the stability of that country’s financial markets and international finance and exchange rates. Among the advanced countries, the United States’ (U.S.) monetary policy is critical to the world’s economy. The U.S. dollar plays a central role among international currencies, with U.S. monetary policy having a significant impact on other countries. The price inflation in Japan and the widening interest rate gap between Japan and the U.S. significantly influence Japan’s market trends. This article provides a detailed study of the factors causing price inflation in Japan and the interest rate gap between Japan and the U.S.
最近の日米金利差と日本の為替レートと 物価上昇率への影響
大石 隆介(OISHI Ryusuke)
要旨
日本の物価水準は2024年に上昇し,消費者に負担をもたらした。各国の中央銀行が設定する政策金利は,その国の金融市場や国際金融・為替相場の安定に影響を与える。先進国の中でも米国(U.S.)の金融政策は世界経済にとって極めて重要である。米ドルは国際通貨の中で中心的な役割を果たしており,米国の金融政策は他国に大きな影響を与える。日本の物価上昇率や日米金利差の拡大は,日本の市場動向に大きな影響を与える。本稿では,日本の物価上昇と日米金利差の拡大要因について詳しく考察する。
連載 バンバラマメ(BAMBARA BEAN)
瀬口 正晴(SEGUCHI Masaharu), 楠瀬 千春(KUSUNOSE Chiharu)
本論文「バンバラマメ(BAMBARA BEAN)」は“Lost Crop of Africa”volume II Vegetables NATIONAL ACADEMY PRESS 2006のBAMBARA BEANを翻訳紹介するものである。
ここ数世紀で,かつては無名だったピーナツは劇的に拡大し,世界有数の作物の一つになった。アフリカにとって特に重要なピーナツ(主に落花生)は,セネガルから中央アフリカ共和国とスーダンから南アフリカに広がる2つの広大なベルトを含むおよそ30カ国に相当な栄養をもたらしている。実際,大陸の観点から考えると,ピーナツはアフリカ最大の食料供給源の一つであり,おそらくトウモロコシ,キャッサバ,モロコシに次ぐものとなるであろう。 驚くべきことは,ピーナツはブラジル原産で,わずか400年前にアフリカの海岸に到達したということである。そしてさらに驚くべきことは,アフリカにも独自の対応物があることである。この対応物は,植物,農学,栄養,料理など,ほぼすべての面で似ている。しかし,この外来作物がますます高みに伸びている一方で,その対応物は,農業科学,食品科学,経済発展,そして世界全体ではほとんど知られていない。
連載 乳および乳製品の素晴らしさ 第17回
牛乳に含まれる乳糖のサイエンス
「乳糖合成能をもつα-ラクトアルブミンの遺伝子変異による誕生」
齋藤 忠夫(SAITO Tadao)
哺乳動物の最大の特徴は,乳(ミルク)を乳腺上皮細胞で生合成して仔に与える点にあります。成獣(大人)になっても乳を摂取している哺乳動物は,地球上ではヒトだけです。ヒトが牛乳を飲む際に,消化ができないために最大の支障となるのは最も含量の多い「乳糖(ラクトース)」です。ヒトは乳児期には乳糖を分解する「乳糖分解酵素(ラクターゼ)」が小腸粘膜にたくさん発現していますが,ヒトは成長につれて乳を飲む機会が段々となくなることでラクターゼも自然と小腸で作られなくなってきます。これは,哺乳動物としては離乳に伴う自然な現象なのです。牛乳を飲むと「おなかゴロゴロ」などと調子が悪くなり不快症状が出ることを「乳糖不耐」と言いますが,決して病気ではありません。
乳腺上皮細胞で乳糖を作るのには,2つのタンパク質が結合した酵素複合体が必要です。その一つのタンパク質にα-ラクトアルブミンという乳清タンパク質があります。このタンパク質が乳腺上皮細胞での乳糖合成機構を制御することが分かって来ました。
今回は,乳糖合成に関わるα-ラクトアルブミンとガラクトース転移酵素の関係,とくにα-ラクトアルブミンがリゾチームから遺伝子進化したことにより,どの様な変化が乳に起こったのかについて考えてみたいと思います。