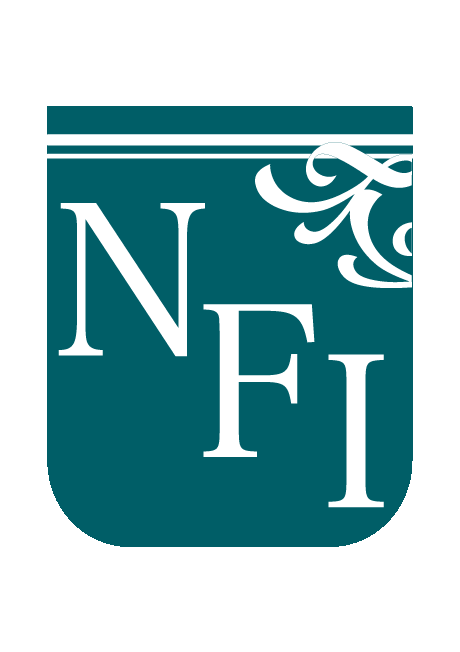New Food Industry 2024年 66巻 5月号
原 著
“H soup (野菜スープ)”摂取による睡眠・便通に関する体感調査
山本 孝徳(YAMAMOTO Takanori),荒谷 公彦(ARAYA Kimihiko),矢澤 一良(YAZAWA Kazunaga)
Internet survey on the effects of “H soup (vegetable soup)” consumption on sleep quality and bowel movements
Authors: Takanori Yamamoto 1*, Kimihiko Araya 1 and Kazunaga Yazawa 2
* Corresponding author: Takanori Yamamoto 1
Affiliated institutions
1 VFOODS CORPORATION [ARAYA HOUSU 5F, 2-7-15, Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo, 104-0031, Japan.]
2 Director, Health Food Science Division, Integrated Institute for Regulatory Science, Research Organization for Nano and Life Innovation, Waseda University
Key Words: diet, vegetables, sleep, constipation, fatigue
Abstract
Objective: To assess changes in sleep quality and bowel movements following “H soup (vegetable soup)” consumption in an Internet survey. Methods: Japanese participants (aged ≥20 years) who were dissatisfied with their sleep quality and bowel movements were recruited in this study via the monitoring recruitment website known as GO-TOROKU (https://www.go106.jp/). The study was conducted between March 19, 2023 and July 4, 2023, and the participants consumed one pack of “H soup” (250 g)/day (at any time) for 2 weeks. Participants answered questions regarding their sleep quality (OSA sleep inventory-Middle Age and Aged version; OSA-MA) and constipation (Japanese version of the Constipation Assessment Scale middle term; CAS-MT), and changes in symptoms before and after “H soup” consumption were compared.
Results: Data were obtained from 299 participants. Following 2 weeks of “H soup” consumption, the participants demonstrated significant improvement in “sleepiness on rising,” “initiation and maintenance of sleep,” “frequent dreaming,” “refreshing,” and “sleep length” of the OSA-MA (P < 0.05), indicating that they felt refreshed upon awakening, slept soundly, and slept better. Furthermore, the participants demonstrated significant improvement in constipation (P < 0.05).
Conclusions: The findings of this study indicate that “H soup” consumption improves subjective sleep quality (feeling refreshed upon awakening, sleeping soundly, and finding it easy to fall asleep) and symptoms of constipation in Japanese adults who are dissatisfied with their sleep quality and bowel movements.
Trial registration: UMIN000050220
Foundation: VFOODS CORPORATION
抄録
目的 本研究では,“H soup(野菜スープ)”摂取による睡眠・便通に関する体感変化をインターネット調査にて評価した。
方法 対象は睡眠の質や便通に不満を持つ20歳以上の日本人男女であり,モニター募集サイトGoトーロク(https://www.go106.jp/)を介して募集した。調査は,2023年3月19日 ~ 2023年7月4日の間で行われ,調査対象者は“H soup”(250 g)を1日1パック,任意のタイミングで2週間継続摂取した。摂取前後で睡眠の質に関する質問(OSA睡眠調査票MA版;OSA-MA)および便秘に関する質問(日本語版便秘評価尺度; CAS-MT)に回答させ,“H soup”(野菜スープ)の摂取による自覚症状の変化を比較した。
結果 回答者は299名であり,“H soup”の2週間継続摂取により,OSA-MAの「起床時眠気」,「入眠と睡眠維持」,「夢み」,「疲労回復」および「睡眠時間」ならびに便秘に関する自覚症状が有意に改善された(P < 0.05)。睡眠の質に関しては,起床時のスッキリ感や熟睡感,寝つきのよさ,さわやかな気分が得られることが確認された。
結論 本調査結果より,睡眠の質や便通に不満を持つ日本人成人男女において,“H soup”の摂取は,自覚する睡眠の質(起床時のスッキリ感や熟睡感,寝つきのよさ,さわやかな気分)および便秘の自覚症状を改善することが示唆された。
事前登録 UMIN-CTR: UMIN000050220
資金提供者 株式会社VFOODS
解 説
健康寿命の延伸のために ―認知症とその予防について―
窪田 倭(KUBOTA Sunao)
わが国の65歳以上の高齢者人口は3,627万人となり,総人口の占める割合は29.1%と過去最高になった1)。65歳以上人口の男女別にみると,男性は1,572万人に対して女性は2,049万人で,性比(女性100人に対する男性人口)は76.7であり,その比は約3対4となっている。また,高齢者人口のうち70歳以上人口は2,872万人(総人口の23.0%),75歳以上人口は1,937万人(同15.5%),80歳以上人口は1,235万人(同9.9%)となっている。高齢者人口の総人口に占める割合は,1950年(4.9%)以後一貫して上昇が続いており,1985年では10%,2005年には20%を超え,現在に至っている。この割合は今後も続くと予想され2040年には35.3%とされている1)。さらに100歳以上の人口は1998年に1万人を超し,以後,年々増加して2023年には92,139人で,女性は81,589人,男性は10,550人となり超高齢化社会を押し上げている2)。 一方で,健康寿命(2019年における)は男性72.68歳,女性は75.38歳と,平均寿命よりそれぞれ約9年,約12年と開きがある3)。この開きはこの10年間短縮されていない状況下にある。健康寿命は「自立した生活が出来る年齢」と定義されているので,人生終末期の約10年間は日常生活に支障をきたす状況下で過ごしていることになっている。
人生終末期の約10年間の日常生活に支障をきたす状態は要介護に導き,医療費増大の大きな要因となってきている。わが国において要介護になった要因について,1位は認知症(18.1%),2位は脳血管障害(15.0%),3位は高齢による衰弱(13.3%),4位は骨折・転倒(13.0%)と報告されている4)。2023年の要介護または要支援の65歳以上の高齢者の認定者数は696.1万人(19.0%),その内,男性が221.3万人,女性が474.8万人となった5)。それに伴い介護保険総額も2000年の3.6兆円から2023年は3.8倍の13.8兆円と増加している6)。
一方,総人口は年々減少し,2023年12月現在,1億2,424万人で前年に比べて減少している7)。さらに,生産年齢の人口は1995年の8,716万人のピークを経て2023年では7,450万人に減少し,2040年には6,000万人になると推定されている8)。2042年には高齢者数は約4,000万人になると推定されていることより,高齢者の医療や介護に対する経済的,社会的負担が生産年齢者層の肩に大きく掛かることとなる。高齢者の健康維持・増進はわが国においての喫緊の課題である。 そこで本稿において健康寿命の延伸の一助として要介護第一位の認知症とその予防について解説する。
たんぱく質の質的評価と主な動植物性たん白の栄養価
卓 興鋼(Kyoko Taku)
要約
たんぱく質の「質」的評価方法にはアミノ酸スコア(AAS),たんぱく質消化率補正アミノ酸スコア(PDCAAS),消化性必須アミノ酸スコア(DIAAS)などがある。アミノ酸スコアをたんぱく質の消化率補正処理したPDCAASが現在でも一般的にたんぱく質の質的評価(栄養価)指標として用いられている。DIAASは,PDCAASより改善したたんぱく質の質的評価として提唱されたが,算出に用いる必須アミノ酸回腸消化率データの蓄積や評価が必要であるため,現時点ではまだ公式に利用が推奨されてはいないが注視しておく必要はある。最新の情報でも,植物性たんぱく質の中でも,大豆たん白の栄養価(PDCAAS)は動物性たんぱく質を含むカゼインや卵白と同じ最高スコア(1.00)で良質と評価されており,大豆たん白素材の栄養面での優位性は示されている。
セロシア(ケイトウ)(CELOSIA)
瀬口 正晴(SEGUCHI Masaharu), 楠瀬 千春(KUSUNOSE Chiharu)
世界の野菜作物の中で,セロシア(ケイトウ)(CELOSIA)は群を抜いて美しい。ギリシャ語の「kelos」(燃える)に由来するこの名前は,この植物の鮮やかな外観と印象的な炎のような花を指している。百カ国で,この種の派手な花序は,庭,ウィンドウ・ボックス,街角のディスプレイ,花の展示などで太陽を凌駕しているように見える。花だけでなく,深い緑色の葉にも赤や紫の色素が混じっていることがある。その結果,セロシアは花が咲く前から人目を引く。セロシアには60種があるが,本章では主にCelosia argenteaを取り上げる。シノニム(類義語)としてよく見かけるのは,セロシア・クリスタータ(Celosia cristata)である。また,セロシア・トリギナ(Celosia trigyna)もある。
乳および乳製品の素晴らしさ 第7回
世界的に注目されるA2ミルク「β-カゼインの特徴と機能特性」
齋藤 忠夫(SAITO Tadao)
日本国内でも最近話題となっている新しいタイプの牛乳に「A2ミルク」があります。一言で表現すると,「A2ミルクとはβ-カゼインの遺伝子型がA2タイプの牛乳」です。日本ではあまり聞きなれない名前の牛乳であり,国内では流通も少ないために,スーパーやコンビニでも常時販売されておらず入手は容易ではありません。 2023年10月には,酪農関係団体の総会であるワールド・デイリー・サミット(WDS)2023が米国ミズリー州のシカゴ市で開催されました。世界55ヵ国から1200名以上の出席者があり,盛大に酪農についての討論や発表がありました。その際に,主催者側が準備したシカゴ市内の「Amazonフレッシュ」という未来型スーパーを視察する機会がありました。アメリカのスーパーで販売されている牛乳の大型のガロンサイズにまず日本人は驚きますが,著者が驚いたのは日本ではまだ市場の確立していないオーガニックミルク,グラスヘッドミルクに加えて「A2ミルク」の常設コーナーがあったことです。日本でも北海道の一部の酪農家や乳業会社が注目して,製造販売が開始されたばかりの新商品です。海外では,ニュージーランドやオーストラリアやアメリカなどが中心となり,その研究や製造販売が盛んのようです。A2ミルクの評価には,研究者間でも賛否両論の情報がありますので,今回はその現状と将来性について考えてみたいと思います。
シリーズ: 世界の健康食品のガイドライン・ガイダンスの紹介 第11 回 ―欧州食品安全機関 (EFSA). 歯と口腔環境に関する機能性評価―
馬場 亜沙美 (BABA Asami),野田 和彦 (NODA Kazuhiko),波多野 絵梨 (HATANO Eri),中村 駿一 (NAKAMURA Shunichi),髙橋 徳行 (TAKAHASHI Noriyuki),LIU XUN,柿沼 俊光 (KAKINUMA Toshihiro),鈴木 直子 (SUZUKI Naoko),山本 和雄 (YAMAMOTO Kazuo)
Introduction to Guidelines or Guidance for Health Food Products in the World: European Food Safety Authority (EFSA) series —Functional Assessment of Teeth and Oral Health— Keywords: european food safety authority, clinical trials, health food, teeth, oral cavity, oral frail
Authors:
Asami Baba1*, Kazuhiko Noda 1, Eri Hatano 1, Shunichi Nakamura 1, Noriyuki Takahashi1, Xun Liu 1, Toshihiro Kakinuma1, Naoko Suzuki 1, Kazuo Yamamoto1
*Correspondence author: Asami Baba
Affiliated institution:
1 ORTHOMEDICO Inc. [2F Sumitomo Fudosan Korakuen Bldg., 1-4-1 Koishikawa, Bunkyo-ku, Tokyo, 112-0002, Japan.]
前回(2024 Vol.66 No.2 掲載,「シリーズ 世界の健康食品のガイドライン・ガイダンスの紹介―欧州食品安全機関(EFSA). 皮膚機能に関する機能性評価―」)に引き続き,欧州食品安全機関(European Food Safety Authority: EFSA)の発行するガイダンス(以下,EFSAガイダンス)について隔月で紹介する。今回は,EFSAガイダンスのGuidance on the scientific requirements for health claims related to bone, joints, skin, and oral health 1)の「5. Teeth and gums」に記載されている,歯と口腔環境に関する機能性評価についてまとめた。本ガイダンスでは歯の正常な発育への寄与が有益な生理学的効果をもたらすと考えられている。ただし,「歯の健康」や「口腔内の健康」,「歯にやさしい(teeth friendly)」といったヘルスクレームは,科学的な評価としてはあまりにも広義すぎるため限定的なヘルスクレームを併記すべきとされ,本ガイダンス1)は歯と口腔環境の評価を5つに分割しているほか,口腔環境に関連する疾病リスクの低減の主張に関する見解が述べられている。 そこで本稿では,本ガイダンス1)に記載される歯と口腔環境のヘルスクレームの根拠となるヒト試験の特徴に焦点を当て紹介する。
世界のメディカルハーブ No.20 ビルベリー
渡辺 肇子(WATANABE Hatsuko)
厳寒に耐える抗酸化ハーブ
ビルベリーは北欧諸国では一般的な森林の灌木で,初夏に開花して夏に甘みと酸味のある小粒の果実をつけます。ビルベリーは日本には自生しませんが,ツツジ科スノキ属の近縁種であるブルーベリーは国内でも見られます。ブルーベリーの仲間は北半球の各地に自生する種があり,日本にはクロマメノキ(Vaccinium uliginosum),シャシャンボ(V. bracteatum),ナツハゼ(V. oldhami)などが知られています。 ビルベリーは高さ30~40cmとひざ丈ほどで,ブルーベリーよりも小さく,摘むには腰を屈めなくてはならないほどです。花色はブルーベリーが白から薄桃色,ビルベリーは赤色で淡緑色のものも見られます。果実はブルーベリーよりも小さめの直径5~10mmで,果皮はブルーベリーよりも濃い黒紫色,内部まで濃い赤紫色をしており,やわらかい果肉とたくさんの種子を持っています。潰すと指が赤く染まるのは,豊富に含まれる色素成分のアントシアニンによるものです。ブルーベリーの果肉は白~淡緑色をしています。また原産もビルベリーと異なり,北米です。